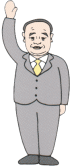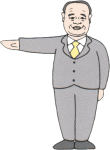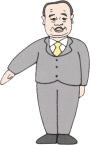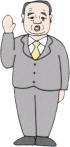| 『オリンピック雑感』 |
| 九州電力柔道部 渡邊 裕二 |
10月下旬,『シカチ氏の謝罪』という記事が某新聞に掲載された。シドニー特派員に よるこの記事は,シドニー五輪柔道男子100kg超級決勝の「誤審」騒動をめぐって,主審を務めたニュージーランド人審判に『シカチ』と名乗る日本人男性が「殺してやりたい」というメールを送りつけたものの,数日後に謝罪をしたというものだった。 4年に一度のスポーツの祭典。各国の代表が母国の威信と己の名誉と誇りを懸けて競い合う檜舞台に世界中の視線が注がれた。(もりろん私自身の視線も・・・) 今回の五輪で日本が獲得した金メダルは5個。初日の女子柔道田村選手の悲願の金メダルに始まり,日本人の底力を見せつけた女子マラソン高橋選手の史上初の金メダルまで,どの場面も実に感動的なものだった。学生時代から柔道に熱中し,現在も柔道に係わり続けている私にとっては,何より日本が獲得した金メダルのうち,実に4個が柔道競技によるものという結果が,たまらなく嬉しく,誇りでもあった。 一方,違う意味でこの5つの金メダルより日本人の心に残った銀メダルがあった。冒頭に書いた柔道男子100kg超級代表の篠原選手が獲得したメダルである。この「疑惑の裁定」については,翌日の新聞に大きく取り上げられ,一般紙までもが一面に掲載したため,多くの方の目に触れることとなった。なかなか柔道の記事が一面に掲載されることはないのだが,今回ばかりは複雑な心境だった。出社すれば,会う人会う人から「あれはどういうことなの」とか「あれは篠原の勝ちでしょう。素人の私にも分かる」とか「あの審判はつまらんね」等々。その度に私も「あれは冷静に見て篠原の勝ち」とか「あの裁定を覆せなかったら,日本柔道は終わりだ」などと言葉とは裏腹に冷静さを欠いた受け答えを繰り返した。その後もしばらくは「あれは篠原の勝ちに違いない」というやや偏った論争が各マスコミで繰り広げられた。私のパソコンにも多くの方から様々な意見がメールで寄せられた。 そんな中,冒頭の記事を読んだ。記事の後半には,篠原選手の試合後のコメント(「弱いから負けた。判定に不満はない」)を引用して,敗者自身も認める正しい判定なのに,日本人が理不尽な脅迫をして,結局は謝った,とニュージーランドでは報じられている,と紹介されていた。また,同日付けの別の新聞には,「もし審判が公明正大であったとしても,篠原はその消極性ゆえに敗れていたはず」とする元柔道世界チャンピオンのコメントを掲載していた。私に送られたメールの中にも「技の優劣は別として,自分の考えを英語で主張できない篠原選手やコーチが悪い」とか「日本人の国民性(奥ゆかしさや謙遜を美徳と考えるところ)だから今回の結果は仕方ない」など日本の教育や国民性にまで言及する意見もあった。  結局,五輪終了後に開催された国際柔道連盟の臨時会議の中で,「誤審は認めつつも,ルール上,判定は覆せない」という訳の分からない結論に達し,日本側としてはこれ以上この問題を論議しない,ということになった。何とも後味の悪い,最悪の結末になった。 東京オリンピックで初めて正式種目に採用されて以来,柔道が「武道」よりも「競技」として世界的に発展するなかで,いつしか「JUDO」となり少しずつ形を変えてきた。カラー柔道着の採用,国際ルールの頻繁な変更などはその最たる例であろう。しかし,こうした変化とは別に「JUDO」となっても失ってはいけないものがある。それは「相手の力を利用して,逆に相手を投げる」という柔道のだいご味であり,そんな「高度な技を見極める目」を育てることである。まだまだ,柔道の宗家としての日本の役割は大きい。 結局,五輪終了後に開催された国際柔道連盟の臨時会議の中で,「誤審は認めつつも,ルール上,判定は覆せない」という訳の分からない結論に達し,日本側としてはこれ以上この問題を論議しない,ということになった。何とも後味の悪い,最悪の結末になった。 東京オリンピックで初めて正式種目に採用されて以来,柔道が「武道」よりも「競技」として世界的に発展するなかで,いつしか「JUDO」となり少しずつ形を変えてきた。カラー柔道着の採用,国際ルールの頻繁な変更などはその最たる例であろう。しかし,こうした変化とは別に「JUDO」となっても失ってはいけないものがある。それは「相手の力を利用して,逆に相手を投げる」という柔道のだいご味であり,そんな「高度な技を見極める目」を育てることである。まだまだ,柔道の宗家としての日本の役割は大きい。今後,こういった不透明な騒ぎを繰り返さないためにも,日本の柔道界が世界をリードしてやるべきことは多いはずだ。 それにしても,オリンピックはすばらしい。柔道をやってて良かった。 |
| (平成12年度 文化期集58号に掲載) |

 渡邊 裕二
渡邊 裕二